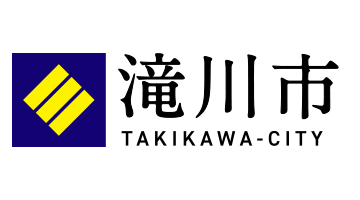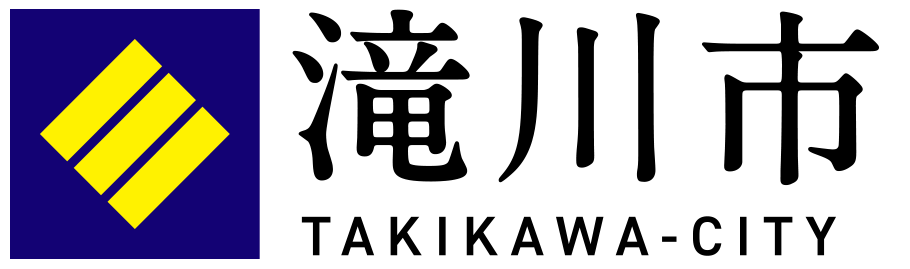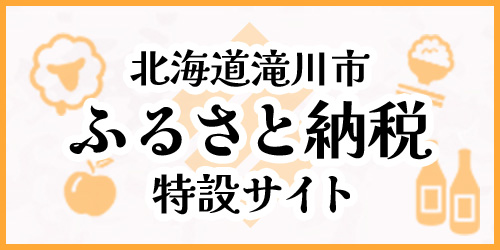本文
国民健康保険制度について
国保年金係からのお知らせ
国民健康保険制度について
国民健康保険(以下、「国保」という。)は、都道府県が財政運営の責任主体となり制度の安定化を目指します。
国保の運営のあり方は、次のとおりです。
| 改革の方向性 | ||
|---|---|---|
| 1.運営のあり方 |
|
|
| 都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
| 2.財政運営 | 財政運営の責任主体
|
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
| 3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4と5も同様 |
地域住民と身近な関係の中、資格を管理 (資格確認書等の発行) |
| 4.保険料の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
|
| 5.保険給付 |
|
|
| 6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 (データヘルス事業等) |
北海道国民健康保険運営方針について
北海道と市町村が一体となり、共通認識の下で国保運営を実施するための、統一的な方針として「北海道国民健康保険運営方針」が策定されました。
北海道国民健康保険運営方針について詳しくは北海道庁ホームページ(国保医療課のページ)<外部リンク>をご覧ください。
滝川市国民健康保険に加入されている方へのお知らせです
年に一回、特定健診はお受けになっていますか?生活習慣病の予防や早期発見のために、毎年、欠かさず受診し、健康管理にお役立てください。
対象者 滝川市国民健康保険に加入されている40歳~74歳の方
特定健診について
市役所職員を名乗った還付金詐欺にご注意ください。
市役所職員を名乗り、金融機関のATMで国保税の還付金を受け取ることができると電話し、逆にATMでお金を振り込ませようとする事例が発生しており、市役所への問い合わせが増えています。
保険医療課では、還付金をお戻しする場合、金融機関のATMに行くよう指示したりすることはありませんので、不審に思われた場合は、市役所並びに警察署へお問い合わせください。
国民健康保険について
私たちは、いつ、どんなときにケガや病気に襲われるかわかりません。そんなときでも、安心してお医者さんにかかれるよう、加入者が日頃からお金を出しあい、必要な費用をまかなうなど、助け合いを目的とした制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除いたすべての方が国保の被保険者となります。
国保の負担割合
医療機関・薬局でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば次の負担で治療が受けられます。
マイナ保険証を利用するためには、事前にマイナポータルで「健康保険証利用の申し込み」の登録をしていただく必要がありますので、ご留意ください。
| 0歳~義務教育就学前 | 医療費の2割負担 |
|---|---|
| 義務教育就学後~70歳未満 | 医療費の3割負担 |
| 70歳以上75歳未満 |
医療費の2割負担 (現役並み所得者は3割) |
国保の加入と脱退
加入する日(国保の資格が発生する日)
- 職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
→国民健康保険への加入には、加入の届出が必要です。 - 転入してきた日(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 子どもが生まれた日
- 生活保護を受けなくなった日
注意 加入の届出が遅れると、加入資格が発生した月まで遡及して保険税を納めなければなりませんので、届出はお早めに行ってください(最高3年まで遡及します)。
例)
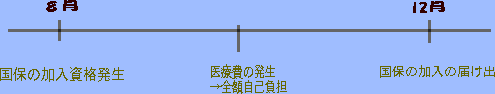
↠この場合、保険税は8月までさかのぼって納めなくてはなりません。
脱退する日(国保の資格がなくなる日)
- 職場の健康保険などへ加入した日または翌日
→国民健康保険の脱退には、喪失の届出が必要です。 - 転出した日
- 死亡した日の翌日
- 生活保護を受けはじめた日
- 後期高齢者医療保険に加入した日の翌日
注意 脱退の届出が遅れると、保険税を二重に支払ったり、国保のマイナ保険証等を使い診療を受けてしまうと国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
保険税について
国民健康保険税は世帯ごとに課税され、納税義務者は世帯主となります(国保に加入していない方も含む)。
保険税を滞納すると
- 督促を受けたり、延滞金が加算されます。
- 医療費をいったん全額自己負担していただきます。
※マイナ保険証をお持ちでない方には、特別療養費(医療費を全額自己負担したあと、申請により払い戻される保険給付相当額の療養費)支給対象者用の資格確認書が交付されます。 - 国保で受けられる給付の全部または一部が差し止められます。
- 国保で受けられる給付の全部または一部が滞納保険税にあてられます。
令和7年度の滝川市の税率
保険税額は被保険者である世帯主および世帯員につき算定した(1)から(3)の合算が年間の額です。
- 医療保険分(基礎課税額)
- 後期高齢者医療保険分(後期高齢者支援金等課税額)
- 介護保険分(介護納付金課税額)
※年度途中で加入または脱退した場合は、加入月数に応じて課税されます。
(1)医療保険分(基礎課税額)
1)平等割額 年間23,100円 1世帯につき
2)均等割額 年間23,100円 加入者1人につき
3)所得割額 9.1% 令和6年中の所得額から基礎控除の43万円を除いた額に対して
1)~3)の合計額が年間の医療保険分になります。
※賦課限度額は、66万円です。
(2)後期高齢者医療保険分(後期高齢者支援金等課税額)
1)平等割額 年間6,600円 1世帯につき
2)均等割額 年間6,600円 加入者1人につき
3)所得割額 2.8% 令和6年中の所得額から基礎控除の43万円を除いた額に対して
1)~3)の合計額が年間の後期高齢者医療保険分になります。
※賦課限度額は、26万円です。
(3)介護保険分(介護納付金課税額)
1)均等割額 年間12,000円 加入者1人につき
2)所得割額 2.3% 令和6年中の所得額から、基礎控除の43万円を除いた額に対して
1)、2)の合計額が年間の介護保険分になります。
※賦課限度額は、17万円です。
国民健康保険税の軽減と減免
低所得者に対する均等割額・平等割額の軽減
加入者(擬制世帯主含む)の前年所得額の合計額が一定基準に満たない場合、所得に応じて均等割額と平等割額が7割、5割、2割軽減されます。
7割:判定基準所得額が 43万円+{(給与所得者等の人数-1)×10万円} 以下
5割:判定基準所得額が 43万円+(被保険者等の人数×30万5千円)+{(給与所得者等の人数-1)×10万円} 以下
2割:判定基準所得額が 43万円+(被保険者等の人数×56万円)+{(給与所得者等の人数-1)×10万円} 以下
※1月1日時点で満65歳以上の年金所得者は、上記基準額に最大で15万円上乗せされます。
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)です。
未就学児の均等割額の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割額が5割軽減されます。低所得者に対する国保税の軽減を受けている世帯は、そこからさらに5割軽減されます(申請は不要)。
出産する予定又は出産した被保険者に係る産前産後期間の所得割額・均等割額の免除
令和6年1月1日から、出産する予定又は出産した被保険者に係る産前産後期間の所得割額、均等割額が免除されます。
・対象 令和5年11月以降に出産(妊娠85日以上の分娩)する予定又は出産した被保険者
※死産、流産(人工中絶を含む。)及び早産の場合も対象
・免除期間
単胎妊娠 ~ 出産の予定日(出産日)が属する月の前月から出産の予定日(出産日)が属する月の翌々月の 計4か月分
多胎妊娠 ~ 出産の予定日(出産日)が属する月の3か月から出産の予定日(出産日)が属する月の翌々月 の計6か月分
・申請の方法
申請は出産予定日の6か月前から可能です。母子健康手帳をご持参のうえ、市役所1階5番窓口までお越しください。
届出書ダウンロードはこちらから(産前産後期間に係る保険税軽減届出書・変更届 [PDFファイル/34KB])
※後日その他の必要書類を求める可能性があります。
非自発的な離職者に対する軽減
解雇や倒産などの非自発的な理由により失業(離職)し、国保へ加入する人の国保税について、失業(離職)から一定の期間、非自発的失業者の前年の給与所得が10分の3として算定され、国保税が軽減されます。雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」が対象となります。軽減の期間は離職した次の日の属する月から、翌年度末までになりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。軽減対象者が対象期間に国民健康保険に再度加入した場合は、残っている対象期間について対象となります。
ただし、離職日時点で65歳以上の人及び雇用保険特例受給資格者は、対象となりません(条例減免により保険税を軽減できる場合もありますので、ご相談ください)。
なお、高額療養費の所得区分判定も同様に10分の3として判定されます。
- 離職理由コード ~ 「11」、「12」、「21」、「22」、「31」、「32」
特定受給資格者:会社のリストラや倒産でやむなく退職した人 - 離職理由コード ~ 「23」、「33」、「34」
特定理由離職者 :期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由により離職した人
※「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由により、公共職業安定所等が行います。
申告の方法
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご持参のうえ、市役所1階5番窓口までお越しください。
申告書ダウンロードはこちらから(非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減申告書[PDFファイル/103KB])
災害や疾病、廃業した自営業など生活困窮者に対する減免
災害等により生活が著しく困難となった場合に、その所得状況等を勘案し、市税条例、市税等減免要綱により国保税が減免される場合があります。
後期高齢者医療制度へ移行することによる軽減
- 低所得者に対する均等割額・平等割額の軽減
国保税軽減世帯から一部が後期高齢に移行した場合、国保税の軽減判定の際に、移行した後期高齢者の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、これまでと同様の軽減措置(7割・5割・2割軽減)が適用されます。
※軽減の期間 ~ 恒久化 - 世帯で賦課される平等割額の軽減
国保から後期高齢者医療被保険者へ移行することにより、国保単身世帯となった場合、移行後5年目までの間は医療分・支援金分の平等割額が半額に軽減され、移行後6年目から8年目までの間は平等割額が4分の1軽減されます。 - 国保以外の医療保険加入者の被扶養者であった者の軽減
国保以外の医療保険の本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その移行者の被扶養者から国保加入となった65歳以上の人は、当分の間、下記のとおり軽減されます。- 所得割額が免除
- 均等割額が国保加入から2年間半額 ※5割、7割軽減世帯を除く
- 国保加入者が旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割額が国保加入から2年間半額 ※5割、7割軽減世帯を除く
国保の給付
- 子供が産まれたら《出産育児一時金》…488,000円
滝川市の国民健康保険加入者で妊娠85日以上の出産(死産・流産含む)をされた場合は、世帯主に488,000円(産科医療補償制度に加入する医療機関において出産された場合は、12,000円を加算)を支給します。
※令和5年3月31日以前の出産については、出産育児一時金は408,000円、産科医療保障制度による加算金は12,000円です。
※直接支払制度とは、原則として保険者から直接医療機関に分娩費用を支払う仕組みで、この制度をご利用される場合は、医療機関等で手続きを行ってください。
分娩費用が出産育児一時金の金額を超えた場合は、超えた金額を医療機関等に支払ってください。
また、分娩費用が出産育児一時金の金額に満たない場合は、その差額を支給しますので、市役所国民健康保険窓口で手続きしてください。
詳細については、保険医療課国保年金係までお問い合せください。 - 加入者が死亡したら《葬祭費》 ……… 30,000円
- 住民税非課税世帯等の人は入院した場合に食事代や居住費の減額を受けられます。
ただし、減額を受けるためには『標準負担額減額認定証』 、もしくは『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要です。
※マイナ保険証での受診に対応している医療機関・薬局では、上記の認定証の提示は不要です。
| 1食あたりの食費 | ||
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 510円 ※1 | |
| 住民税非課税世帯の人 (70歳以上では低所得IIの人) |
90日までの入院 | 240円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院 | 190円 | |
| 70歳以上で低所得Iの人 | 110円 | |
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食当たり510円・居住費1日当たり370円を自己負担します。
| 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 510円 ※2 | 370円 |
| 住民税非課税世帯の人 低所得II |
240円 | 370円 |
| 低所得者I | 140円 | 370円 |
※2 一部医療機関では470円
医療費の負担が大きくなったら《高額療養費制度》
(この手続きは、電子申請可能です。)
医療費の支払いが高額になった場合、下記の自己負担限度額を超えた分が申請により、後日高額療養費として支給される制度です。診療月の翌月の一日から2年間で時効となりますのでご注意ください。
70歳未満の人の場合
計算は月の一日から末日まで1か月単位で行い、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算されます。差額ベッド代、食事代等は対象となりません。
また、同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合(それぞれの医療機関で、入院・外来・医科・歯科別に)、それらを合算して下記の自己負担限度額を超えた分が申請により支給されます。
入院および外来(※)で高額な医療費がかかった場合、医療機関での支払いを限度額までとすることができます。
その場合『限度額適用認定証』(住民税非課税世帯の方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』)が必要となりますので、あらかじめ市役所にて交付申請を行ってください。
※マイナ保険証での受診に対応している医療機関・薬局では、上記の認定証の提示は不要です。
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 4回目からの限度額 |
|---|---|---|
| 901万円超 | 252,600円 | 140,100円 |
| さらに実際にかかった医療費が842,000円 を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算します | ||
| 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円 | 93,000円 |
| さらに実際にかかった医療費が558,000円 を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算します | ||
| 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円 | 44,400円 |
| さらに実際にかかった医療費が267,000円 を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算します | ||
| 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
70歳から75歳未満の方の場合
入院および外来(※)で高額な医療費がかかった場合、医療機関での支払いを限度額までとすることができます。
なお、低所得者II・低所得者Iに該当する方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要となります。
さらに平成30年8月より、現役並み所得者I・現役並み所得者IIに該当する方にも限度額適用認定証が必要になりますので、あらかじめ市役所にて交付申請を行ってください。
※マイナ保険証での受診に対応している医療機関・薬局では、上記の認定証の提示は不要です。
| 外来(個人ごと) | 外来と入院(世帯ごと) | ||
|---|---|---|---|
| 現 役 並 み 所 得 者 |
III(課税所得690万円以上) | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 4回目以降※3 は140,100円 |
|
| II(課税所得380万円以上) | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 4回目以降※3 は93,000円 |
||
| I(課税所得145万円以上) | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 4回目以降※3 は44,400円 |
||
| 一般 | 18,000円 ※1 | 57,600円 4回目以降※2 は44,400円 |
|
| 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者I | 15,000円 | ||
※1 年間(8月~翌年7月)限度額 144,000円
※2 過去12か月以内に【外来+入院(57,600円)】の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合。
※3 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合。
1) 現役並み所得者 …
同一世帯に現役並み所得以上(住民税の課税標準額が145万円以上)の70~74歳の国保加入者がいる場合。ただし、70~74歳の国保加入者の収入の合計が、1人世帯で383万円未満(2人以上世帯で520万円未満)の場合は、申請により「一般」の区分と同様になり、2割負担となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税標準額が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保加入者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」を適用します。
2) 低所得者II …
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人 (低所得者1を除く)
3) 低所得者I …
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費控除(年金の場合は80万円、給与所得の場合は給与所得から10万円を控除して計算)を差し引いたときに0円となる人。
高額な医療費と介護費用がかかったとき《高額医療・高額介護合算制度》
医療費が高額になった世帯に、介護保険受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの限度額を適用後、年間の自己負担額を合算した額が一定の限度額(一年間(8月~翌年7月)で判定)を超えた場合に、その超えた分が支給されます。
70歳未満の方の場合
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 901万円 超 | 212万円 |
| 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
| 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
| 210万円以下 | 60万円 |
| 住民税 非課税世帯 |
34万円 |
70歳以上75歳未満の方
| 所得区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 課税所得 | 690万円以上 | 212万円 |
| 380万円以上 | 141万円 | |
| 145万円以上 | 67万円 | |
| 一般 | 56万円 | |
| 低所得者II | 31万円 | |
| 低所得者I | 19万円 | |
特定の病気で長期療養を要するとき
人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病、HIVなどの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたる医療が必要な場合、医師の診断書を添えて市役所窓口に届出をすれば「特定疾病療養受療証」の交付を受けられます。これを医療機関に提示すれば、月額で10,000円(人工透析が必要な70歳未満の人で所得区分が600万円を超える者は20,000円)の自己負担になります。
交通事故にあったら
交通事故等傷害の原因が第三者によるもので、国保で治療を受けられた場合は届出が必要です。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談した場合、国保が使えなくなる場合がありますので必ず示談をする前にご相談ください。
※届出についてはこちらをご覧ください→交通事故など第三者の行為でケガをしたときは・・・ [PDFファイル/648KB]
医療費の一部負担金の支払免除
国民健康保険に加入している方が保険医療機関に入院する場合に負担する一部負担金について、災害により重大な損害を受けたときや、失業等により収入が著しく減少したときなどの理由により、生活が困難となった場合において、申請により一部負担金の支払が免除となる場合があります。
免除の該当要件
- 自然災害による農作物の不作、不漁などにより収入が減少したとき
- 災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記に掲げる事由に類する事由があったとき
上記の該当要件にあてはまる場合であっても、資産等の状況によっては免除を受けられない場合があります。詳しくはご相談ください。
申請書等ダウンロードはこちらから(一部負担金免除申請書・収入申告書・意見書)
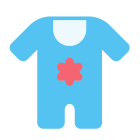 妊娠・出産
妊娠・出産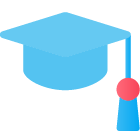 入園・入学
入園・入学 就職・退職
就職・退職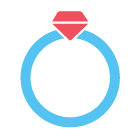 結婚・離婚
結婚・離婚 住宅・引越し
住宅・引越し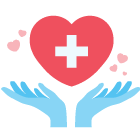 けが・病気
けが・病気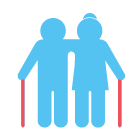 高齢・福祉
高齢・福祉 おくやみ
おくやみ 申請・届出
申請・届出 ゴミ
ゴミ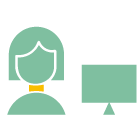 相談窓口
相談窓口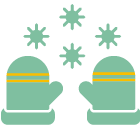 雪情報
雪情報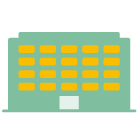 施設利用状況
施設利用状況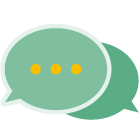 SNS
SNS 分類でさがす
分類でさがす カレンダーでさがす
カレンダーでさがす 組織でさがす
組織でさがす 地図でさがす
地図でさがす