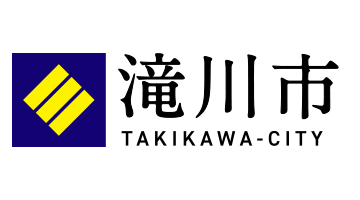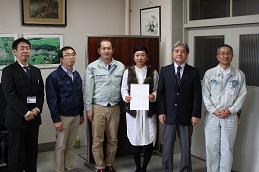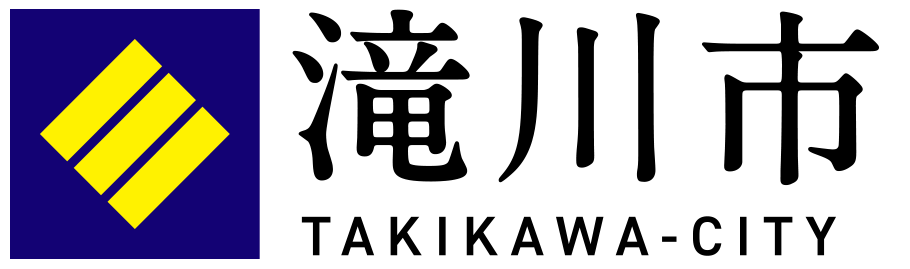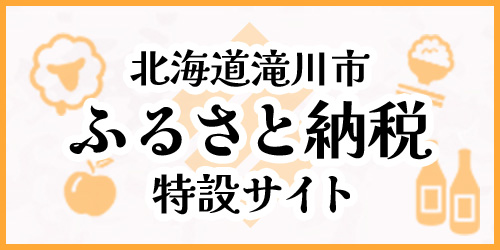本文
滝川農業塾第4期生研修の様子
滝川農業塾第4期生修了式及び研修報告会 平成29年3月27日 NEW
この度、2年間の研修カリキュラムを終えた4期生の修了式及び研修報告会を開催いたしました。
当日は、各関係機関から多くのご臨席を賜り、滝川農業塾長である前田市長から4期生それぞれに修了証書が手渡されました。その後の研修報告会では、2年間の研修報告や修了後の抱負などについて、4期生は晴れやかな表情で発表していました。
4期生の皆さん、2年間の研修お疲れ様でした。
エゴマ加工流通視察研修報告会 平成29年3月22日
塾生は、前日実施した視察研修で学んだ内容を地域へフィードバックするため、市内で雑穀(エゴマ含む)を作付けする生産者に向けた視察研修報告会を開催しました。
報告会では、実需者による滝川産エゴマの評価や他地域と滝川市との栽培方法の違いなどについてプレゼン。
エゴマの収量向上に向けた新たな技術を把握するため、塾生の説明に、参加者は真剣に耳を傾けていました。
エゴマ加工流通視察研修 平成29年2月22日~24日
この度塾生は、それぞれが生産するエゴマの搾油技術などを学ぶため、先進地である岐阜県と愛知県へ視察研修に行きました。
岐阜県の日本エゴマ普及協会においては、エゴマ摂取による効果などのご説明をいただいたほか、実際に、専用の搾油機で搾油していただきながら、具体的な搾油技術や品質保持の重要性を教えていただきました。
次に、エゴマ油を日本で初めて食用として商品化した愛知県の太田油脂(株)では、世界的なエゴマをめぐる情勢や全国的な需要動向、さらにはエゴマの栽培方法のコツなど、幅広いお話をいただきました。なかでも、あまり聞き覚えのない名称の「オイルテイスティング」では、原料や搾油方法などの異なる油の味を比較し、それぞれの特徴を学びました。
今回の研修において、塾生は収量向上につながる生産技術に触れることができたほか、将来、滝川市におけるエゴマの搾油、さらにはその商品化に向けた多くのヒントを得たことと思います。
花・野菜技術センター専門技術研修(第1回目) 平成29年2月20日
地方独立行政法人北海道立総合研究機構 花・野菜技術センターの「専門技術研修」受講の様子です。
塾生は、今年度一度「専門技術研修」を修了しましたが、更なる技術習得のため、「ナス科作物の播種、接ぎ木技術の習得」をテーマに専門技術研修を受講することとなりました。
研修一回目となる当日は、接ぎ木に用いる台木用ナスの播種作業を行いました。
※ 本研修は5期生も受講していることから、続きは、「滝川農業塾第5期生研修の様子」をご覧ください。
関連リンク
花・野菜技術センターでは、平成29年度北海道花き・野菜技術研修(総合技術研修)研修生の追加募集を行っております。
詳しく知りたい方は、こちらをご覧下さい。
地方独立行政法人北海道立総合研究機構花・野菜技術センター<外部リンク>(ホームページへリンク)
水稲・畑作研修会 平成28年10月26日

空知農業改良普及センター中空知支所主催の「水稲・畑作研修会」。
研修会では、近年問題となっている水稲の病害虫や防除方法、小麦の雪腐病やなまぐさ黒穂病の特徴や対策などについて説明があり、塾生は真剣に研修に参加していました。
花・野菜技術センター専門技術研修(第20回目) 平成28年10月21日
6月から約5ヶ月間にわたって学んだ、花・野菜技術センター「専門技術研修」の修了式です。
塾生の研修にご尽力いただいた職員の皆様立ち会いのもと、花・野菜技術センターの長沢場長から塾生に修了証書が手渡されました。その後の懇談では、本研修で学んだ技術などを今後の経営に活かしていきたいと、塾生は晴れやかな表情で話していました。
花・野菜技術センター専門技術研修(第15~19回目) 平成28年9月26日、28日、10月6日、7日、12日
「専門技術研修」の最終段階。
塾生は、第15回目から第19回目の5日間にわたって、これまで研修で行った調査結果をもとに、品種ごとの特性の違いなどを検証した上で、報告書にまとめあげる作業を行いました。
調査・集計した数値をグラフにまとめるなど慣れない工程でしたが、塾生は真剣に報告書作成に取り組んでいました。
エゴマ圃場視察(塾生相互訪問) 平成28年9月29日
近年、滝川市ではエゴマやイナキビなど雑穀の作付が拡大しているところですが、今回はエゴマを作付けする4期生同士の情報交換を目的に、塾生のエゴマ圃場の視察を行いました。
当日は、空知農業改良普及センター中空知支所の普及指導員にも同行していただき、それぞれの圃場の生育状況や栽培方法の違いなどについて学んだほか、今後の滝川市における雑穀の展望などについて、塾生同士熱心に意見を交わしていました。
花・野菜技術センター専門技術研修(第13・14回目) 平成28年9月12日、21日
第14回目となる「専門技術研修」は、前回に引き続きミニトマトの収量調査を行いました。
今回で収穫作業を含めた技術的な研修は終了。今後は、これまでの生育調査や収量調査の結果を踏まえ、品種による特性の違いなどについて検証していくこととなります。
花・野菜技術センター専門技術研修(第9・10・11・12回目) 平成28年8月17日、23日、30日、9月7日
花・野菜技術センターの「専門技術研修」。
今回は、ミニトマトの誘引作業を行ったのち、6品種それぞれについて、一果実の平均的な重量である「平均一果重」(良果収量・重量/良果個数)などを測定する収量調査を行ったほか、研修の番外編として、他の研修生の圃場巡回に同行し、花きや野菜(いちご、たまねぎ、オクラなど)の栽培状況などを視察しました。
水稲・小麦研修会 平成28年8月23日
塾生は、空知農業改良普及センター中空知支所が主催する「水稲・小麦研修会」に参加しました。
研修会では、水稲の農薬や新規除草剤の紹介のほか、近年管内で発生が見られる小麦なまぐさ黒穂病の対策などについて説明があり、塾生は真剣に説明に耳を傾けていました。
花・野菜技術センター専門技術研修(第7・8回目) 平成28年8月9日・12日
花・野菜技術センターにおける「専門技術研修」第七・八回目です。
第七回目の当日は、ミニトマトの定植40日後の生育調査として、6品種それぞれについて、「第一花房の着果数」や「草丈」、「葉数」、「茎径」を調査しました。
その後、全ての品種ではありませんでしたが、ついにミニトマトの初収穫。6月の定植から始まった研修ですが、きれいに色づいたミニトマトの収穫に、塾生は喜びもひとしおの様子でした。
花・野菜技術センター専門技術研修(第4・5・6回目) 平成28年7月22日・26日・8月2日


花・野菜技術センターにおける「専門技術研修」の続報です。
7月22日、26日、8月2日に、第四回~第六回目となる研修を実施しました。
塾生は、トマトの品種による生育の違いなどについて指導を受けながら、ハウス内の暑い中、脇芽取りや誘引作業などを一生懸命行っていました。
花・野菜技術センター専門技術研修(第3回目) 平成28年7月15日
花・野菜技術センターにおける「専門技術研修」第三回目です。
今回は、前回定植したミニトマトの脇芽(わきめ)取りと支柱立て、さらにカボチャの結実確認を行いました。
研修では、それぞれ多数の品種を栽培しており、今後、その生育の違いなどを勉強していきます。
ミニトマトは、「イエローピコ」「キャロル10」「キャロル7」「アイコ」「シンディスイート」「CF千果」。
カボチャは、「味平DX」「くりゆたか」「雪化粧」「えびす」「ほっとけ栗たん」。
とてもたくさんの品種がありますが、皆さんはどれだけご存じでしょう。食べ比べも楽しいですね。
道外先進地視察研修 平成28年7月11日~13日
7月11日~13日の2泊3日で、第4期生が岩手県と青森県に視察研修に行きました。
岩手県の花巻農業協同組合では、雑穀の栽培方法や販売状況について研修したほか、岩手県農業研究センター県北農業研究所(軽米町)では、雑穀栽培時の雑草抑制の研究についてのお話を伺いました。また、町内のえごま生産者で運営しているえごまの搾油施設も視察しました。
青森県では、にんにくで有名な田子町でにんにくの産地化の取り組みについて研修し、横浜町ではなたねの生産者と栽培技術などについて意見交換を行いました。
かなりハードなスケジュールでしたが、それぞれの視察先で貴重なお話を伺うことができ、大変有意義な視察研修となりました。
なたね搾油室視察 平成28年7月6日
日本有数の作付面積を誇る滝川市のなたね栽培。
第4期生は、全員なたねを栽培していることから、JAたきかわ「菜の花館」にあるなたね搾油室の視察を行いました。自分達が栽培したなたねがどのように加工され、そして商品になっていくのかについて真剣に学んでいました。
花・野菜技術センター専門技術研修(第2回目) 平成28年6月30日



第二回目となる花・野菜技術センターにおける「専門技術研修」では、カボチャの整枝作業に係る指導を受けたほか、トマトの定植作業を行いました。
一口に「トマトの定植作業」と言っても多くの工程があります。この機会に、研修当日の作業の流れをご紹介します。
まず、「マルチ」という土の上にかぶせたビニールに、ホーラーという道具でトマトを植える穴(植え穴)を開けます。次に、植え穴に土壌施用粒剤(殺虫剤)を処理した上で、苗を植え付け(定植)します。その後、水やりをした苗を仮支柱へ結束し、ハウスの外に防風網を設置して、定植作業は完了となりました。
空知青年農業者夏期研修会 平成28年6月21日
空知4Hクラブ連絡協議会と空知総合振興局が主催する、空知青年農業者夏期研修会に参加しました。
研修先である(有)ほなみ(南幌町)では、畑作を主体とする大規模法人経営のノウハウを学んだほか、有機JAS認定農産物を販売する(有)大塚ファーム(新篠津村)においては、無農薬・低肥料による栽培方法や経営者としてのあるべき姿などについて、大塚代表より熱く語っていただきました。
また、最後に視察した新篠津村加工トマト部会では、近年需要の拡大する加工用トマトの露地における栽培方法を学ぶなど、将来空知の農業を担っていく参加者にとって非常に有意義な研修になったことと思います。
花・野菜技術センター専門技術研修(第1回目) 平成28年6月16日
滝川市にある地方独立行政法人北海道立総合研究機構 花・野菜技術センターの「専門技術研修」受講の様子です。
研修課題は、「カボチャ及びトマトの仕立て方の習得」。
研修一回目となる当日は、まずカボチャの品種特性などについて指導を受けた後、ハウスで育てた苗を畑に植える定植作業を行いました。
関連リンク
花・野菜技術センターについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧下さい。
地方独立行政法人北海道立総合研究機構花・野菜技術センター<外部リンク>(ホームページへリンク)
中間報告会 平成28年4月19日
滝川農業塾第5期生の入塾式とあわせて、第4期生の中間報告会を行いました。
入塾してから1年が経過し、これまでの研修で学んだことや2年目に向けた抱負などを報告してもらいました。また、中間報告会後自治会を開催し、2年目に向けた研修計画について話し合いました。
道内先進地視察研修 平成27年8月26日
道内の先進事例の視察として、3軒の農業者を訪問しました。1軒目は江別市美原地区で農業生産法人を立ち上げ経営している(株)輝楽里さんにおいて、複数戸による法人設立の意義や経緯を中心にご説明をいただきました。2軒目は当別町の(有)大塚農場さんを訪問し、新たな作物の導入可能性を探るべく当別町を中心に栽培されている亜麻について学ばせていただきました。3軒目に、新篠津村の(有)大塚ファームさんを訪問し、有機栽培や6次産業化の取り組みについてご説明をいただきました。3軒の皆さんとも、取り組まれている内容は様々でしたが、根底には「より良い作物を作るためには、経営をより発展させるためにはどうしたらいいか常に考え、実行している」様子が共通して感じられ、視察後の塾生から「とても勉強になりました」と感想が聞かれました。
北海道立農業大学校(農業経営者育成研修) 平成27年6月8日~12日
基礎研修である農業経営者育成研修の受講のため、北海道立農業大学校(農大)に1週間泊まり込みでの研修です。道内他地域からの受講者らとともに昼は研修を、夜は宿舎で交流をして、最終日には課題解決調査のテーマ発表を行いました。今回の研修のほかにも、機械研修などで農大へは今後も受講する機会があります。
秋まき小麦の生育調査 平成27年4月27日、5月1日、22日
北海道立農業大学校の経営者育成研修を受講するにあたり、各自で課題を設定して半年間の調査研究があることから、4期生共通の作物である秋まき小麦の生育調査を行うこととなりました。空知農業改良普及センター中空知支所の普及指導員の方から小麦の生育過程や生育状況の確認方法を教えてもらったあと、塾生たちの圃場をまって生育状況を確認しました。
滝川農業塾第4期生入塾式 平成27年4月16日
平成27年4月16日に滝川農業塾第4期生の入塾式が行われました。
入塾式の後には自治会を行い、基礎研修の科目選択やステップアップ研修で学びたいこと、年間スケジュールの確認などをしました。
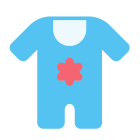 妊娠・出産
妊娠・出産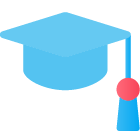 入園・入学
入園・入学 就職・退職
就職・退職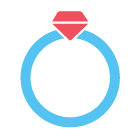 結婚・離婚
結婚・離婚 住宅・引越し
住宅・引越し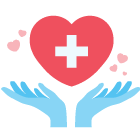 けが・病気
けが・病気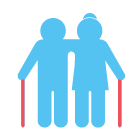 高齢・福祉
高齢・福祉 おくやみ
おくやみ 申請・届出
申請・届出 ゴミ
ゴミ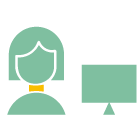 相談窓口
相談窓口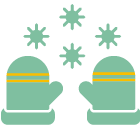 雪情報
雪情報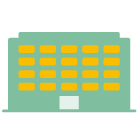 施設利用状況
施設利用状況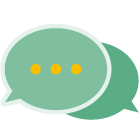 SNS
SNS 分類でさがす
分類でさがす カレンダーでさがす
カレンダーでさがす 組織でさがす
組織でさがす 地図でさがす
地図でさがす