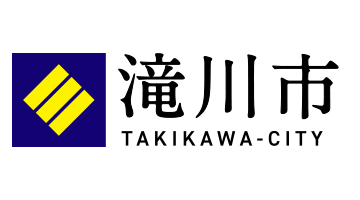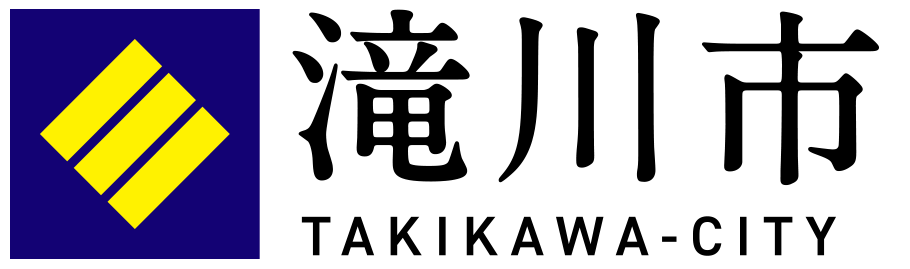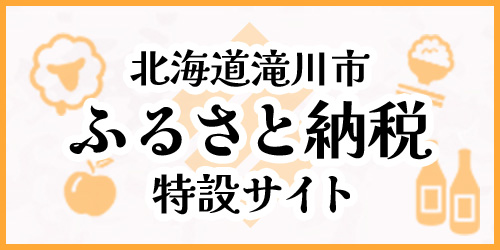本文
滝川農業塾第5期生研修の様子
滝川農業塾第5期生修了式及び研修報告会 平成30年4月10日
平成30年3月27日に、2年間の研修カリキュラムを終えた5期生の修了式及び研修報告会を開催しました。
当日は、各関係機関から多くの方のご出席をいただき、塾長である前田市長から5期生それぞれに修了証書が手渡されました。その後の研修報告会で、塾生達は2年間の研修を踏まえた今後の目標などを力強く発表していました。
5期生の皆さん、2年間の研修お疲れ様でした。
花・野菜技術センター総合技術研修(3) 平成29年8月4日
塾生は、総合技術研修の一環として、花・野菜技術センター「公開デー2017」で販売実習を実施。
イベント開始前から多くの来場者が集まる中、塾生は研修で担当するイタリアンナスやピーマンをはじめ、他の研修生が生産した農産物の販売を行いました。
研修受講前から、多くのイベントで農産物を販売してきた経験もあることから、塾生はとても慣れた様子で販売実習に取り組んでいました。
フォークリフト運転技能研修 平成29年6月27日~28日
塾生は、北海道立農業大学校のフォークリフト運転技能研修を受講しました。
研修では、フォークリフトの構造や取扱方法をはじめ、運転に必要な力学などについて学んだ後、学科と実技の技能検定試験を受け、塾生達はみごとに合格となりました。
花・野菜技術センター総合技術研修(2) 平成29年6月20日
花・野菜技術センター「総合技術研修」場内ミーティングの様子。
場内ミーティングとは、栽培演習として、研修生達がそれぞれ管理を担当する品目の生育状況や栽培方法などを確認し合う場。
ナスやピーマンなどを担当する塾生は、これまでの栽培方法に加え、特に注意して管理したポイントなどをわかりやすく説明していました。
花・野菜技術センター総合技術研修(1) 平成29年5月25日
花・野菜技術センター「総合技術研修」の様子。
4月11日に行われた開講式後、塾生は、野菜の栽培方法などについて、基礎から応用まで日々熱心に学んでいるところですが、今回はナスの定植作業を行いました。
今後、定植した多品種のナスが、異なる条件下(温室栽培、ハウス栽培、露地栽培)でどのように生育するのか、どのような違いを示すのかなどを確認し、その結果について考察していくこととなります。
花・野菜技術センター総合技術研修開講式 平成29年4月11日
滝川市にある(地独)北海道立総合研究機構 花・野菜技術センターの「総合技術研修」開講式の様子。
今年度、本研修の野菜コースを受講することとなった塾生は、今後10月6日までの約半年間、講義、演習、実習及び視察研修などを通して、基礎理論から実践技術までを体系的に学ぶこととなります。
開講式では、花・野菜技術センターの場長より激励のお言葉をいただき、塾生もやる気に満ちた表情をしていました。
滝川農業塾第5期生中間報告会 平成29年4月10日

平成29年4月10日に滝川農業塾第6期生入塾式とあわせて、第5期生の中間報告会を行いました。
中間報告会では、1年間の研修で学んだことや残り1年で学びたいことなどを報告いただき、その後の自治会では、農業塾修了生の助言をいただきながら、今年度の研修スケジュールなどを確認しました。
花・野菜技術センター専門技術研修(第11~18回目) 平成29年3月30~31日・4月1~5日・7日
花・野菜技術センター「専門技術研修」の最終段階。
塾生は、それぞれ接ぎ木を行った株がしっかり活着しているかの確認を行ったほか、活着の成否を決めた原因などについて検討を行いました。
今回の研修で学んだことは、将来、自身の野菜生産の安定化や発展に確実に活かされていくことでしょう。
花・野菜技術センター専門技術研修(第6~9回目) 平成29年3月17日・21日・27日・28日
花・野菜技術センター「専門技術研修」(第6~9回目)。
塾生はこれまで台木・穂木の生育管理を行ってきましたが、今回ついに、研修テーマである「接ぎ木」を実施しました。
当日はまず、台木と穂木の切り口を合わせる「幼苗斜め接木法」という手法のレクチャーを受けた後、それぞれ接ぎ木を実施。かなり緻密な作業ではありましたが、作業を繰り返すうちに、塾生はコツを得た様子でした。
花・野菜技術センター専門技術研修(第4~5回目) 平成29年3月9日・13日
花・野菜技術センターの「専門技術研修」(第4~5回目)の様子。
塾生は、前回に引き続きトマトやナスの台木・穂木の生育状況を確認したほか、今回の研修テーマである「接ぎ木」実施に向けた、今後の作業スケジュールなどの打合せを行いました。
花・野菜技術センター専門技術研修(第3回目) 平成29年3月6日



花・野菜技術センターの「専門技術研修」(第3回目)。
今回は、2月20日に播種したトマトの台木と、3月2日に播種したトマトなどの穂木の生育状況を確認しました。
※ 写真は、左から「トマトの台木」、「トマトの穂木」。一番右の写真は、土の温度を定期的に測定する温度データロガ-という機器。
花・野菜技術センター専門技術研修(第2回目) 平成29年3月3日
花・野菜技術センターの「専門技術研修」(第2回目)です。
この度、野菜を作付けしている塾生2名(4期生1名、5期生1名)が、「ナス科作物の播種、接ぎ木技術の習得」をテーマに本研修を受講。
第2回目となる今回は、接ぎ木に関する講義を受けた後、ナスやトマトの播種作業を行いました。
※ 第1回目の受講の様子は、「滝川農業塾第4期生研修の様子」をご覧下さい。
「水稲」生育調査結果発表(課題解決研修) 平成28年12月13日~15日

農業大学校「農業経営者育成研修(初級)」の課題解決研修「水稲生育調査」結果発表。
11月に発表を行った塾生に続き、第2陣目として第5期生のうち2名が、水稲生育調査結果の発表を行いました。
塾生はそれぞれ、スライドに文字を入れた写真を使用するなど、工夫した発表に努めたほか、生育調査の結果を踏まえた、自身の経営における今後の対策などをわかりやすく説明していました。
北海道スマート農業フェア 平成28年12月1日
塾生は、今回が初開催となる「北海道スマート農業フェア」(主催:北海道スマート農業フェア実行委員会)に参加しました。
フェアは、スマート農業に係る各種セミナーや道内外の先進技術(約60社)を紹介する技術展示ブース、アシストスーツの体験装着、屋外展示エリアにおける自動操舵トラクターの体験試乗などなど、非常に充実した内容。
塾生は多くの技術展示ブースに足を運び、様々な先進技術について積極的に学んでいました。
「水稲」生育調査結果発表(課題解決研修) 平成28年11月15日~17日
農業大学校「農業経営者育成研修(初級)」の最後のカリキュラム、課題解決研修「水稲生育調査」の結果発表です。
第5期生の先陣を切って塾生のうち1名が研修に参加(※他の2名の塾生は、12月に参加予定)。3日間に渡る研修では、6月から行ってきた「水稲生育調査」の手法や結果をスライドにまとめ、最終日に、他の研修生の前で自身の調査結果の発表を行いました。
その後の閉講式では、研修生を代表し塾生が修了証書を授与。農業大学校の校長からは、研修生達に対する期待と励ましのお言葉をいただきました。
平成28年度農業簿記通信講座 スクーリング 平成28年11月9日~11日



農業大学校の「農業簿記通信講座」スクーリング(面接授業)の様子です。
塾生は、7月から10月までの毎月、農業簿記に係る通信講座を受講しておりましたが、その総まとめとして3日間のスクーリングを受講。
スクーリングでは、初日に農業経営における簿記の必要性などを学んだのち、これまで通信講座で学んだ知識を確認するため、2日間にわたる演習も行われました。
「水稲」生育調査集合研修(第五回目) 平成28年11月8日
農業大学校の課題研修である「水稲生育調査」の総まとめ。
当日は、これまでに引き続き、空知農業改良普及センター中空知支所の普及指導員にご指導をいただきながら、6月から行ってきた水稲生育調査結果の分析・検証を行いました。
今後、各塾生は本日の分析結果を踏まえ資料を作成し、農業大学校において発表することとなります。
「水稲」生育調査集合研修(第四回目) 平成28年9月13日
今回は、集合研修の第四回目として、水稲の稔実調査を行いました。
稔実調査とは、株ごとの総籾(もみ)数と、そのうち実の入っていない不稔(ふねん)籾数を測定し、稔実歩合(実の入っている籾の割合)を算出し、今年の収量予測に活用するというものです。
簡単に言えば、塾生の試験圃場から刈り取った株ごとの籾の数を、黙々と数えるという地道な作業でしたが、結果は不稔割合(実の入っていない籾の割合)で約5%と、中空知管内の平年値と同程度。
収穫を間近に迎えるこの時期、6年連続の豊作に向けて期待が高まる結果となりました。
農業機械高度利用研修(中級) 平成28年8月29日~9月2日
塾生は、先週に引き続き、北海道立農業大学校(本別町)における農業機械高度利用研修(中級)を受講しました。
研修では、トラクターの運転操作と取扱い作業などについて学んだのち、学科と実技の技能検定試験を受け、5期生全員みごとに合格となりました。
農業機械高度利用研修(初級・総合コース) 平成28年8月23日~26日
北海道立農業大学校(本別町)における農業機械高度利用研修(初級・総合コース)受講の様子です。
研修では、4日間の日程でトラクターの基本操作から点検・整備の方法などを学びました。
塾生は今後卒業までに中級・上級を受講し、最終的には「北海道指導農業機械士」の認定を受ける予定です。
「水稲」生育調査集合研修(第三回目) 平成28年8月19日
集合研修の第三回目です。
前半は、空知農業改良普及センター中空知支所の普及指導員から、管内の水稲生育状況について説明を受けたのち、カメムシなどの病害虫防除について、さらには「水稲直播栽培」という栽培方法などについて研修を受けました。
後半は、普及指導員の指導を受けつつ、各塾生の試験ほ場の生育調査を実施。管内平均と自身の調査結果を比較しながら、今年の生育状況を確認していました。
【4・5期生合同】農協制度研修 平成28年8月9日
滝川農業塾のステップアップ研修として、農協制度研修を開催しました。
研修では、たきかわ農業協同組合より事業(購買事業・営農指導事業・販売事業)の概要について説明をいただいたのち、意見交換を実施。塾生は、日頃から疑問に思っていたことや要望事項など積極的に発言し、有意義な研修となりました。
【4・5期生合同】先進地視察研修報告会 平成28年8月9日
今回、塾生の発案により、滝川農業塾として初の試みとなる先進地視察研修報告会を開催しました。
本ホームページにおいて紹介しているとおり、今年度、第4期生は道外、第5期生は道内の先進地を視察しましたが、その研修内容を共有するとともに、塾生同士で意見交換を行い互いに研さんを積むことが目的。
当日は、第4期生・第5期生それぞれから視察内容について発表があったのち、和気あいあいとした雰囲気の中、自由闊達な意見交換が行われました。
道内先進地視察研修 平成28年7月26日~27日
今回第5期生は、「自然農法」「短角牛」「農業女子」をキーワードに、1泊2日で道内の先進地視察を行いました。
まず、「自然農法」として、三世代にわたって64年間自然農法を続けている秋場農園(北見市)と、鉄人の秀さんと称される伊藤自然農園(訓子府町)を視察。無肥料・無農薬による自然農法は、基本技術をしっかり守り、信念を持って取り組むことの重要性を学びました。
次に、国内でも頭数の少ない「短角牛」を肥育する北十勝ファーム(有)(足寄町)では、国産飼料にこだわった肥育方法を学んだほか、畜産業界の情勢と今後の方向性など、幅広いお話をいただきました。
締めくくりとなる「農業女子」は、士幌町の夢想農園。元レストランシェフという経歴をもつ旦那さまと“農業女子”として活躍する奥さまからは、固定観念にとらわれないエネルギッシュな活動などについてお話いただいたのち、おすすめの「わかもろこし」(トウモロコシが大きくなる前のヤングコーン)の試食。ヒゲまで食べることができ、とてもおいしかったです。
今回の研修は、かなり幅広い分野の取組についてお話を伺うことができ、塾生にとってかなり刺激になったことと思います。
「水稲」生育調査 平成28年7月22日
課題研修である水稲生育調査は、空知農業改良普及センター中空知支所の普及指導員から生育調査の方法などについてご指導をいただく集合研修のほかに、その指導を踏まえ、実際に塾生だけで各自のほ場の生育調査を実施する形ですすめています。
前日の集合研修に続き、この日は塾生が集合し、第三回目となる生育調査を実施しました。
6月に雨天が続いたことで生育が心配されていたところですが、生育調査の結果をみると、7月からの好天も味方してか塾生の水稲は回復傾向。収穫が楽しみです。
「水稲」生育調査集合研修(第二回目) 平成28年7月21日
北海道立農業大学校の課題研修である、水稲生育調査の集合研修を行いました。
前回同様、空知農業改良普及センター中空知支所の普及指導員から、生育ステージに沿った生育調査方法について指導を受けた後、病害虫防除などについて質疑応答を行いました。
【4・5期生合同】水稲現地研修会 平成28年7月15日
農業塾第5期生と第4期生は、空知農業改良普及センター中空知支所が開催する「水稲現地研修会」に参加しました。
現地研修会では、新しい水稲除草剤の効果について、実際に滝川市などで行った試験結果を踏まえた説明があったほか、今年の水稲の生育状況などについて報告がありました。
よりおいしい滝川産のお米を作るため、塾生は真剣に研修会に参加していました。
「水稲」生育調査集合研修(第一回目) 平成28年6月14日
農業塾第5期生は、北海道立農業大学校の課題研修として、水稲の生育調査に取り組みました。
初回となる今回はあいにくの雨天でしたが、空知農業改良普及センター中空知支所の普及指導員から生育調査方法について指導を受けた後、実際に圃場で生育調査を実施しました。
滝川農業塾第5期生入塾式 平成28年4月19日
平成28年4月19日に滝川農業塾第5期生の入塾式が行われました。
入塾式の後には自治会を行い、基礎研修の科目選択やステップアップ研修で学びたいこと、年間スケジュールの確認などを行いました。
※集合写真は、第5期生と第4期生合同。
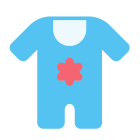 妊娠・出産
妊娠・出産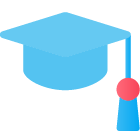 入園・入学
入園・入学 就職・退職
就職・退職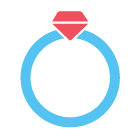 結婚・離婚
結婚・離婚 住宅・引越し
住宅・引越し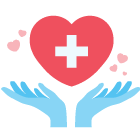 けが・病気
けが・病気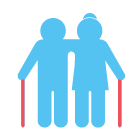 高齢・福祉
高齢・福祉 おくやみ
おくやみ 申請・届出
申請・届出 ゴミ
ゴミ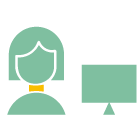 相談窓口
相談窓口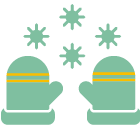 雪情報
雪情報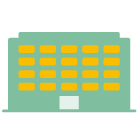 施設利用状況
施設利用状況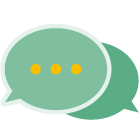 SNS
SNS 分類でさがす
分類でさがす カレンダーでさがす
カレンダーでさがす 組織でさがす
組織でさがす 地図でさがす
地図でさがす