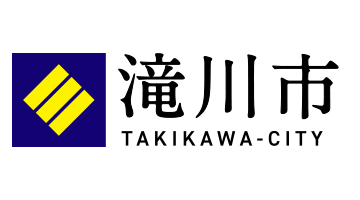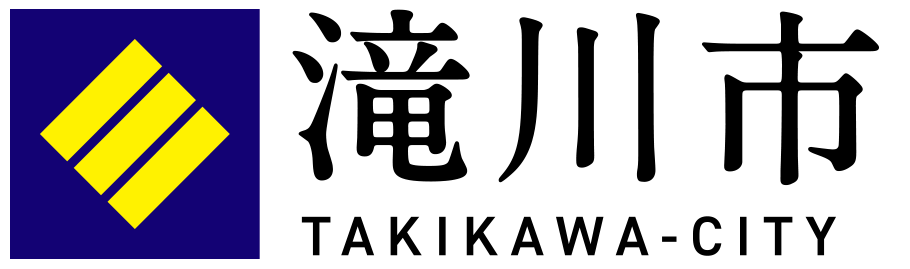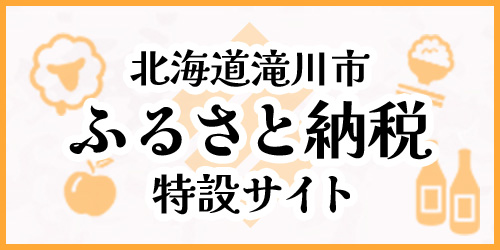本文
滝川市のプロフィール(歴史)
歴史
 滝川市の語源は、アイヌ語の「ソーラプチ」=「滝下る所」を意訳したものです。また、空知川の中流には滝のような段差がありアイヌの人々から「ソーラプチペツ」=「滝のかかる川・滝の川」と呼ばれており、滝川という地名がつけられました。
滝川市の語源は、アイヌ語の「ソーラプチ」=「滝下る所」を意訳したものです。また、空知川の中流には滝のような段差がありアイヌの人々から「ソーラプチペツ」=「滝のかかる川・滝の川」と呼ばれており、滝川という地名がつけられました。
滝川市の歴史は、明治23年北海道庁令第1号によって滝川村戸長役場がおかれたことに始まります。この年、北方の警備と開拓のため屯田兵440戸が入植し、同27年には江部乙に400戸の屯田兵が入植して開拓が進められ、これら屯田兵の往来と生活物資の供給、上川道路の開削に伴う資財の供給で滝川は大いに栄えました。
明治31年上川鉄道の開通、水害の発生で滝川市は、交通の要衝としての地位を失うとともに水害の被害で大きな打撃を受けましたが、大正2年滝川と道東を結ぶ上富良野線(現根室本線)の開通によって再びその地位を回復しました。
昭和に入ってから石炭産業の隆盛によって赤平・芦別など産炭地からの石炭をはじめとする物資の輸送が活発になり、滝川市発展の礎となりました。
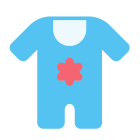 妊娠・出産
妊娠・出産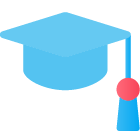 入園・入学
入園・入学 就職・退職
就職・退職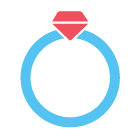 結婚・離婚
結婚・離婚 住宅・引越し
住宅・引越し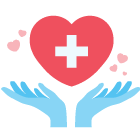 けが・病気
けが・病気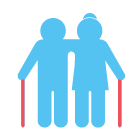 高齢・福祉
高齢・福祉 おくやみ
おくやみ 申請・届出
申請・届出 ゴミ
ゴミ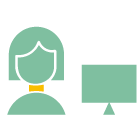 相談窓口
相談窓口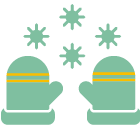 雪情報
雪情報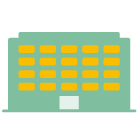 施設利用状況
施設利用状況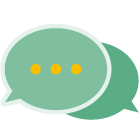 SNS
SNS 分類でさがす
分類でさがす カレンダーでさがす
カレンダーでさがす 組織でさがす
組織でさがす 地図でさがす
地図でさがす