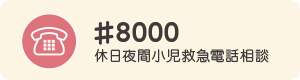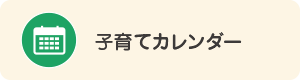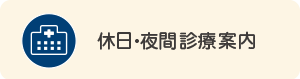本文
幼児教育・保育の無償化について
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点等から、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります。
令和元年10月1日からの利用料について
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が、令和元年5月に公布されました。
この法律に基づき、令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子ども、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無料となります。
その他、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設、就学前の障がい児の発達支援などについても無料となることがあります。
幼児教育・保育の無償化の制度について詳しく知りたい方は、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
- 幼児教育・保育の無償化の概要<外部リンク>(こども家庭庁ホームページ)
- 幼児教育・保育の無償化の主な例(イメージ図)<外部リンク>(こども家庭庁ホームページ内PDF)
- 給食費の取り扱いについて[PDFファイル/139KB]
幼稚園・認可保育所・認定こども園等について
※子ども・子育て支援新制度移行幼稚園(滝川幼稚園・滝川白樺幼稚園など)を利用されている方は、
「保育所・幼稚園一覧表」のページをご覧ください。
対象者・利用料
- 幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無料となります。
- 幼稚園については、月額上限25,700円です。
- 無償化の期限は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無料となります。
- 0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料となります。
さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、利用料の多子軽減制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントし、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料となります。
※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
対象となる施設・事業
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料となります。
※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育・認可外保育施設等の利用について
対象者
幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育・認可外保育施設とも、無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※認可保育所、認定こども園(保育部分)等を利用できていない方が対象となります。
※「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同様の要件)があります。
詳しくは、下表「保育を必要とする事由」をご確認いただき、認定の申請を行ってください。
利用料
- 幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用している場合、幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用料に加え、利用日数に応じて最大月額11,300円までの利用料が無料となります。
- 認可外保育施設等を利用している場合、3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無料となります。
対象となる施設・事業等
認可外保育施設に加え、一時的保育事業、病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を対象とします。(以下「認可外保育施設等」という。)
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指しますが、お住まいの市町村により、その利用を対象外としている場合があります。
施設等利用費の請求について
- 利用料の無償化については、償還払い(これまでと同様にいったん利用料を利用施設に納めていただき、その後、申請により払い戻す方式)を行っております。
償還払いを行うためには、市(担当課)に請求申請を行っていただく必要があります。市指定の請求書様式に利用施設から発行された領収書等を添付し、市(担当課)に請求申請してください。 - 幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育の無償化に伴う認定の概要はこちら [Wordファイル/112KB]
- 認可外保育施設等の無償化に伴う認定の概要はこちら [Wordファイル/116KB]
就学前の障がい児の発達支援について
就学前の障がい児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります。
保育を必要とする事由
認定を受けるには、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当する必要があります。認定を希望する場合は、下表をご確認いただき無償化認定の開始前(認定希望日より前)に認定の申請を行ってください。
| 保育の必要性の事由 | |
|---|---|
| 就労 | 家庭内外で就労している場合(※勤務時間帯を問わず1か月60時間以上の就労をしていること) |
| 妊娠・出産 | 出産前後のため、その児童を保育することができない場合 (認定期間:産前7週から産後の翌日8週後の属する月の末日まで) |
| 疾病・障害 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神・身体に障害を有しており、保育することができない場合 |
| 介護・看護等 | 長期にわたり疾病の状態にあるか、または精神・身体に障害を有する同居の親族を常時介護しており、保育することができない場合 |
| 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっており、保育することができない場合 |
| 求職活動 | 求職活動(起業準備を含む。)を行っていて、保育ができない場合 (認定期間:認定日から起算して90日が経過する日が属する月の末日まで) ※ただし、児童1人につき1回のみ |
| 就学 | 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)のため、保育ができない場合(認定期間:就学中) |
| 虐待やDVのおそれがある場合 | |
| 育児休業中 | 既に対象事業施設等を利用していて、継続利用が必要な場合(認定期間:原則、1歳の誕生日前日が属する月の末日まで(最長2歳の誕生日前日が属する月の末日まで)) |
※既に認定を受けていて、認定状況に変更が生じる場合※
無償化の認定を受けている認定期間中で、次のような状況の変更が生じる場合は、認定の解除または変更の手続きを行う必要がありますので、事由の変更が生じる前に必ず担当課までご連絡願います。
必要に応じた書類のご提出を依頼します。
- 認定要件がなくなる場合
退職、勤務時間の短縮により要件を満たさなくなるなど - 認定要件が変更になる場合
- 転職による就労先変更
- 保育を必要とする事由の変更(例:就労から妊娠・出産へ変更になるなど)
- 婚姻や離婚など、世帯員の異動による世帯構成の変更
その他、変更の手続きが必要か判断しかねる場合は、担当課までお問い合わせください。
申請書ダウンロード
| (1)認定等の際に必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 施設等利用給付認定・変更申請書[その他のファイル/403KB] | 保育の必要性の認定を受けるための申請書 (幼稚園預かり保育・認可外保育施設等共通) ※申請は、当該申請書に加え、上記の(1)~(9)の保育必要事由により添付する書類が異なりますので、下表を確認の上、併せて添付書類のご確認・ご準備をお願いします。 |
| 施設等利用給付認定・変更申請書(記入例)[Excelファイル/55KB] | |
| 施設等利用給付認定変更届[Wordファイル/30KB] | 認定要件の変更・世帯構成の変更など、ご家庭の状況等が変わった場合や、認定の期間が変更になる場合に提出が必要な届出 |
| 施設等利用給付認定変更届(記入例)[Wordファイル/38KB] | |
| (2)償還払の際に必要な書類 | 備考 |
| 施設等利用費申請書兼請求書(幼稚園預かり保育用)[Wordファイル/58KB] | 施設に支払った利用料を償還するための請求書※保育の必要性の認定を受けた方が対象です |
| 施設等利用費申請書兼請求書(幼稚園預かり保育用・記入例)[Wordファイル/77KB] | |
| 施設等利用費申請書兼請求書(認可外保育施設等用)[Wordファイル/61KB] | |
| 施設等利用費申請書兼請求書(認可外保育施設等用・記入例)[Wordファイル/80KB] | |
| 活動報告書[Wordファイル/19KB] | 各事業所が認定保護者の利用実績に応じて発行する書類 (活動報告書は、ファミリーサポートセンター利用による無償化認定を受けている方が提出する様式です。) |
| 活動報告書(記入例)[Wordファイル/28KB] | |
| 特定こども・子育て支援提供証明書兼領収書[Wordファイル/33KB] | |
| 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(認可外保育施設用・一時預かり事業用・幼稚園預かり保育事業用・記入例)[Wordファイル/99KB] |
保育の必要性の認定を受けるために申請書と併せて必要な書類等
| 保育の必要性の事由 | 必要な書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 就労 | 就労証明書 | 勤務先からの証明(保護者1人につき1枚) ※勤務時間帯を問わず1ヵ月60時間以上の就労をしている証明が必要です。 |
|
自営業申告書 |
事業主からの申告(認定児童1人につき1枚) |
|
| 農業就労等申告書 | 事業主からの申告(認定児童1人につき1枚) | |
| 妊娠・出産 | 母子手帳の写し | 母親の名前と出産予定日がわかるもの |
| 疾病・障害 |
|
|
| 介護・看護等 | 介護が必要な方の医師からの診断書等 | |
| 求職活動 | 求職活動(起業準備)状況申告書 ※添付書類:求職活動を証明するもの |
本人の申告 ※ハローワークに行っている場合は、ハローワークカードまたはハローワーク受付票の写し |
| 就学 | 在学証明書 ※添付書類:就学していることがわかるもの |
※時間割が確認できる書類の写し |
| 育児休業中 | 就労証明書 |
育児休業を取得している期間等の証明 |