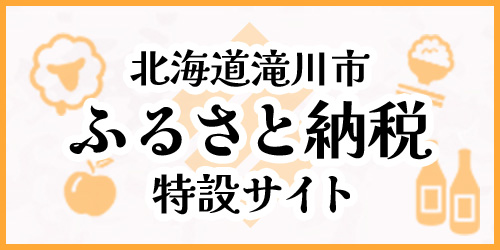本文
ジンギスカンの歴史

※参照:滝川市郷土館・展示より
北海道を代表する郷土料理のひとつ「ジンギスカン」はルーツに諸説ありますが、タレ漬けの味付けジンギスカンについては「ルーツは滝川種羊場、普及は松尾ジンギスカン」といった認識は誰もが否定できない事実であるとされています。
羊毛が軍服の大切な素材となっていた頃、第一次世界大戦時に輸入が途絶え、大正7年に政府が羊毛の国内自給をめざした「綿羊百万頭計画」を打ち出し、滝川や札幌の月寒など全国5カ所に種羊場が開設されました。その際、羊毛だけでなく、羊肉の様々な活用方策が研究されるようになり、試行錯誤の末、現代のジンギスカンが誕生しました。
もっとも、庶民の料理として広まったのは戦後のことで、値段が安いわりに美味しかったことが理由とされています。
「羊肉料理・成吉思汗」のレシピは、山田喜平(元滝川種羊場長)が昭和6年に発行した「緬羊と其飼ひ方」に記載されているものが最初といわれています。また、「ジンギスカン」の名付け親は、当時、南満州鉄道株式会社の調査部長であった「駒井徳三」であるという説が一番有力とされています。
ジンギスカンの食べ方は、焼いた肉にタレを付けて食べる「札幌式」と、タレに漬け込んだ肉を焼いて食べる「滝川式」があり、北海道内でも地域によって食べ方が異なります。
滝川市ではじめてジンギスカンが市民に提供されたのは昭和30年、滝川会館とされていますが、そのジンギスカンは札幌式(タレが別皿で用意される)だったそうです。
滝川式(タレ漬け)のジンギスカンは種羊場による各種講習会や綿羊実習生などによって、各地に広められて行き、次第に食味として定着していったとされております。その流れの中で昭和31年、松尾羊肉店はジンギスカンによる企業化をしたことをきっかけに滝川式のジンギスカンが普及しはじめたとされております。
現在ジンギスカンは、北海道をはじめ多くの国民に親しまれる料理となり、平成16年3月には『4月29日を「羊肉(ヨーニク)の日」』として日本記念日協会に認められたほか、同年10月には「北海道遺産」に選定されています。